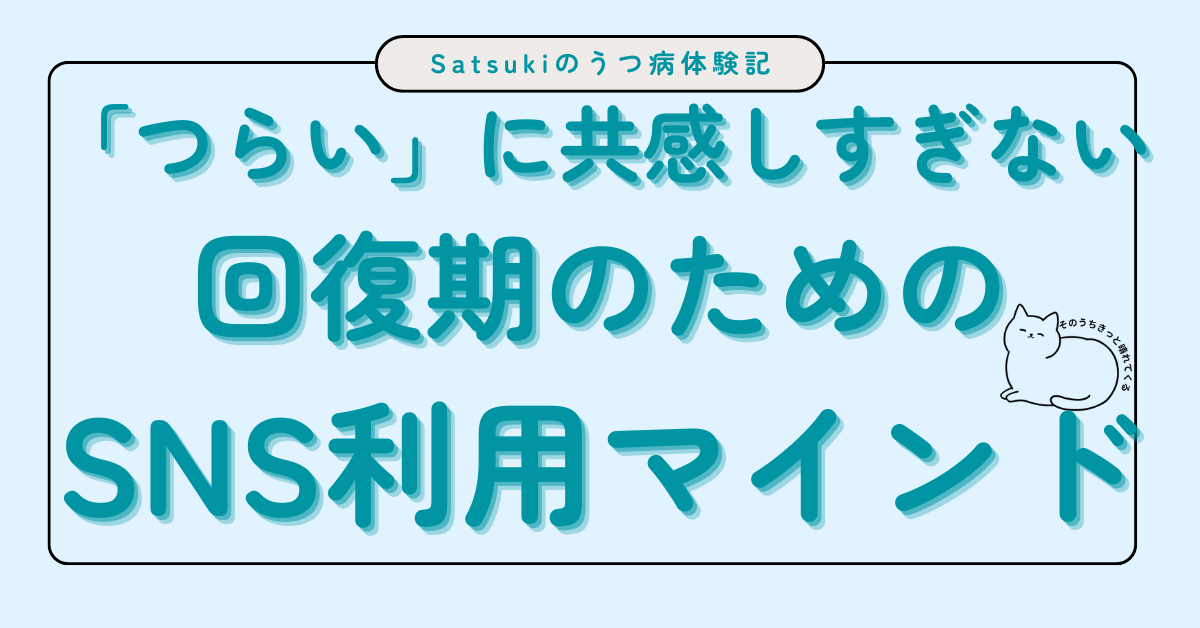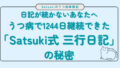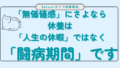はじめに:SNSの利便性
最近は、スマートフォンなしでは生活が難しいくらいの時代になりました。その分、情報量が格段に増えています。
特にX、Instagramなどに代表されるSNSの発達と普及は10年前はだれも想像していなかったようなレベルになっています。
今回は、この情報過多な状態とうつ病という特性を持って付き合う際の注意点についてお伝えしていきます。
情報量の爆増
現代人の1日の情報量は平安時代の一生分
「現代人が1日に扱う情報量は、過去の時代と比べて何倍になったか」という話は、「情報爆発」を象徴するデータとして非常によく引用されます。
正確なデータは計測方法や定義によって異なりますが、一般的に言われているのは、「現代人が1日に受け取る情報量は、江戸時代の1年分、あるいは平安時代の一生分に相当する」という研究結果です。
このデータは、情報科学者や認知科学者が、過去の書籍や新聞の発行部数、現代のインターネットのトラフィック量などから類推・換算して導き出したものです。人が接触するすべてのメディアから受け取る情報量をビットやバイトといったデータ量に換算して類推したようです。
あくまで比喩的なものでしょうけども、脳の負担はすごいことになっていそうです。その分、脳は進化できているんだろうかと心配になります。
さらに爆増傾向
最近では、更に増えているという研究データもあります。
結論として、スマートフォンが普及する前の2010年頃と比べて、人間が「接触できる情報量」は数百倍、数千倍、あるいはそれ以上に増加していると考えるのが妥当だと言われています。
さすがに直近のたった15年程度の期間で、脳の情報処理能力が進化したとは到底思えません。
情報過多は「脳疲労」に直結する
このような膨大な情報量に常にさらされている現代において、「脳疲労」や「情報過多シンドローム」は、多くの人が抱えるメンタルヘルスの問題として認識されています。
特に、うつ病を抱えている方にとっては、情報過多が症状の悪化につながるリスクが高まります。
脳疲労が起こるメカニズム
脳が過労状態になる主な原因は、前頭前野(ぜんとうぜんや)の機能低下です。
脳疲労がうつ病の回復に与える影響
脳疲労によって前頭前野の機能が低下すると、以下のような症状が現れ、うつ病の症状と重なったり、悪化させたりする可能性があります。
私もそうでしたがうつ病がひどい時は、「自分に対する嫌悪感」を強く感じます。
しかしこうやって見てみると、その嫌悪感の根源の大半は「自分が悪い」から発生しているのではなく、「前頭前野の機能が低下している」から発生しているのです。
こうやって冷静に見てみると、「自分はダメな人間だ」と自己嫌悪に陥るのは、なんの解決にもならないことが分かります。自分は悪くないのですから。
精神衛生への影響
SNSは、使い方次第で孤立感を和らげたり、情報を得たりするメリットもありますが、うつ病の症状を悪化させるリスクもあります。
他人との比較による落ち込み
SNSを見ると、楽しそうな写真や文章、キラキラした生活が溢れています。それを見て、自分と比べてしまい、「それに比べて自分は・・・」となりがちです。
私もそうでした。元々は他人と比べるような性格ではなかったのですが、そんな私ですら「楽しそうだな。人生うまくいっているんだな。」と感じていました。
なにせ、自分はまともな日常生活すら過ごせず、一日の大半はベッドの天井を見る生活です。望んでいる生活ではありませんし、「○○がしたい」という感情すら失われた状態です。世の中から置いて行かれたような、自分だけすべてが停止したような、そんな状態なのですから。
ネガティブな情報への過敏な反応
以前の記事にも書きましたが、うつ病がひどい時はYouTube配信者がついた悪態ですら自分のことを言っているように聞こえてしまいます。
そのため、SNSで偶然流れてきた批判的な内容、攻撃的な内容からダメージを受けてしまうことがあります。
批判的な内容や攻撃的な内容からは、ダメージを受けるのが想像できたので極力避けるようにしていました。しかしそれ以外にもダメージを受けてしまうものがあることを想像できていませんでした。
ショッキングなニュース
私がダメージを受けたのは、能登半島地震についてでした。元日に起きたということもあり、状況が気になりました。そのためその日の夜、ベッドに入ってからXを開いたのです。次々と衝撃的なものが目に飛び込んできました。
その頃の私は、ある程度日常生活を過ごせていました。妻の実家で過ごし、たまに買い物にも行ける程になっていました。
しかし、そのニュースに長く触れたことでなんと1週間、ベッドから起き上がれなくなりました。正月なのに起き上がることができなくなってしまい、妻の両親にも申し訳なく思いましたが、どうすることもできませんでした。
ようやく動けるようになり病院で受診した際に、ショッキングなニュースに触れるとそのようなことが起きる場合があると説明されるまで、自分でも原因だとは気づきませんでした。
ネガティブな吐露(共感疲労のリスク)
うつ病になると、孤立しているような感覚が強くなります。その感覚を和らげるために、同じうつ病の人の発信を探す方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私は、あまりSNSを多用する方ではなかったのでうつ病の人のアカウントを探すようなことをしたことがありませんでした。しかし、今回このような「うつ病への理解を深めてもらい、うつ病と前向きに戦っていける情報を発信する」というブログを作ったことで、初めて「#うつ病」という検索をしました。
自分の体験をどう発信すれば役に立つのかを知りたかったのです。当然様々なポストがあります。そして、「つらい」「苦しい」などの感情の吐露も多くありました。うつ病はなかなか共感してもらえない病気だと、私は思います。
「分かってほしい」という気持ちは痛いほど分かります。そのため、SNSで似た境遇の人を見つけて、共感してもらうということが癒しになる場面も多々あると感じます。
ただ、私の場合はその感情の吐露の波に飲まれた結果、3日ほど動けなくなりました。
私は現在、自分でも「ずいぶんと回復している状態だ」と感じています。睡眠薬も卒業しました。日常生活も過ごせるようになり、一日中横になっていないといけないという日は最近ありませんでした。
しかし、感情の吐露の波に触れたことで半年ぶり以上に「まったく動けない」という状態になってしまったのです。
これは、私の性格もあると思いますのですべての人が当てはまるわけではないと思います。しかし、「同じ境遇だから」という理由だけで、ネガティブな感情の吐露に触れ続けるのは悪影響があるかもしれません。
とるべき対策
うつ病からの回復のためには、どういう対策が有効なのかを知っておく必要があります。
時間と場所のルールを決める
最も重要なのは、寝る前のスマートフォン利用を断つことです。 脳が興奮するのを防ぎ、睡眠の質を守るため、就寝時間の1時間前にはスマホを別の部屋に置くなど、物理的に距離を置く対策を推奨します。また、「食事中は見ない」「朝起きてすぐは情報を見ない」など、見る時間と場所を限定するルールを決めましょう。
私は、朝起きてすぐにスマートフォンで情報を見る習慣を辞めました。辞めて気づいたことですが、起きてすぐ膨大な情報に触れることは脳にかなりの負担がかかっていたようです。辞めた期間を挟んで、久々に見た時はぐったりと大きな疲労感を感じました。
この朝の時間は、新しい情報で脳を消耗させる代わりに、横になったままでもできる「軽いストレッチ」など、自分を整える活動に使う時間として確保することが、回復への近道です。
「切り取られた世界」だと意識する
楽しそうな投稿は「その人の一面」と割り切ることが必要です。海外旅行に行っている人も、実は仕事はうまくいっていないかもしれません。高級ランチの映像を流している人も、実は家庭ではカップ麺ばかり食べているかもしれません。その人の「一番いい場面」を切り取っただけなのです。
極端に言えば、花嫁としてウエディングドレスを着ている人と、寝起きでまだパジャマを着ている自分を比較して、「キラキラしていていいな」と言っているだけなのです。
その花嫁も、次の日にはすっぴんのパジャマ姿になるのです。人生のどこを切り取っているかの違いです。
情報源を厳選する
SNSはうまく使えば、癒しにもなります。問題は、何が発信されてくるかです。発信内容が攻撃的であったり、自分には合わないものに触れる必要はありません。
特に、共感による疲労(共感疲労)を防ぐため、フォローするアカウントや検索するハッシュタグを限定し、「自分の回復」を最優先事項として設定することが大切です。
自分に合わない情報源の100個や200個がないくらいで、世の中から取り残されるようなことは現代ではありえません。
何が悪影響を及ぼすのかを知る
どういう情報が精神衛生的に良くないのかを、把握することが大切です。私はそれを知らなかったがために、知らず知らずのうちにショッキングなニュースに過剰に共感し、ダメージを負いました。
大きなニュースであるほど、「触れない」という選択は難しいと思います。しかし、「悪影響があるかもしれない」と準備することで、触れる時間の長さや心構えを変えることはできます。
回復に向けて
SNSは今、すごく身近にある存在です。体が動かないからこそ、手元で手軽に使える便利さの恩恵はあります。しかし、その手軽さゆえに使い方には注意を払う必要があります。
脳も体も、情報量に耐えうるエネルギーがなくても手に取れてしまうのがスマートフォンです。情報が溢れている現代だからこそ、触れる情報について自分で内容を選んだり、量を調整したりする必要があります。
うつ病は脳で不具合が起きています。それを修復する大切な療養期間です。脳にしっかり休んでもらうためにも、SNSの使い方には細心の注意が必要です。
【重要】免責事項と信頼性について
ここに掲載している内容は、すべて私個人の実体験と、一般的な知識に基づいてお話ししています。
この記事は、医師や医療専門家による医学的な診断、治療、またはアドバイスを代替するものではございません。
医学的根拠はございません。専門的な治療が必要な場合、必ず内科・脳神経外科、または心療内科・精神科などの専門医の意見を仰いでください。
当記事を参考に、読者の方が下した判断や行動の結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
合わせて読んでほしい:
うつ病は「脳の通信制限」:情報処理能力が崩壊し、「暇」すら感じなくなるメカニズム
うつ病からの回復に役立った「三行日記」:1244日継続できたSatsuki式マインドセット