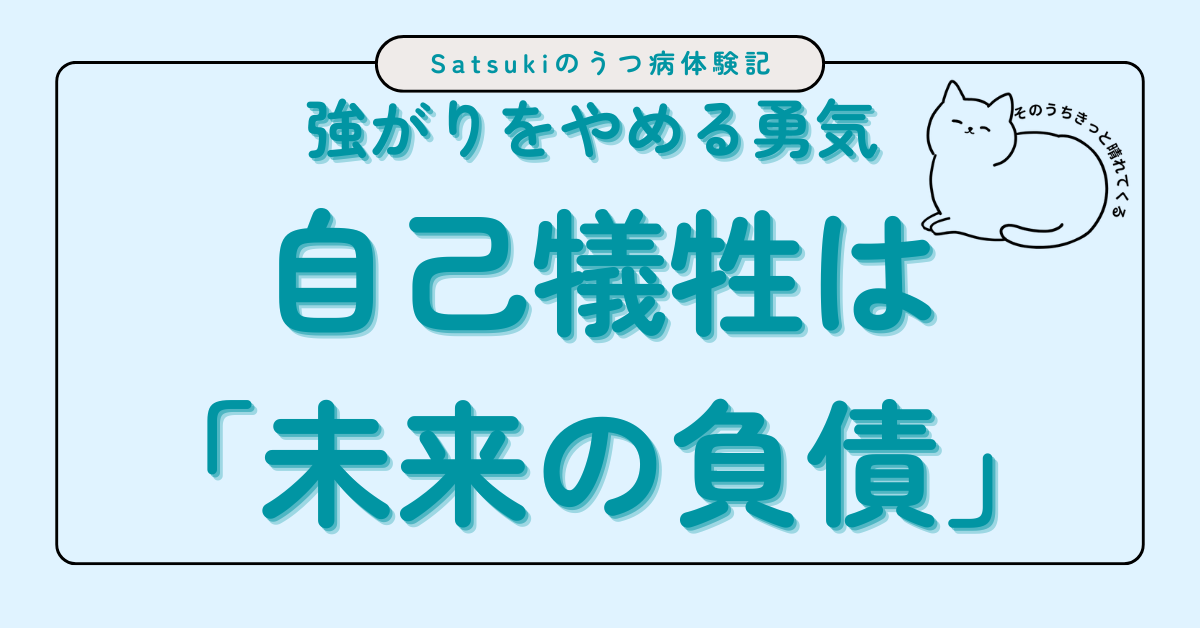はじめに:強がりをやめる勇気
「寒い日には震えて、雨の日には濡れ、雷には怯える」
これは人間として当たり前の事実です。しかし、うつ病から回復を目指す私たちは、この当たり前の事実を否定する強がりを続けてしまいます。
「大丈夫」「平気だよ」と笑うたびに、私たちの脳は疲弊し、回復に必要なエネルギーは失われていきます。
強がりは長期間にわたり『正しい』と信じ込まされてきた自己防衛の仕組みです。私も自分が感情の二重処理をしていることにさえ気づかず、ただ疲労が蓄積する現状を受け入れていました。この気づきこそが、回復への第一歩です。
この記事では、「感情の事実をそのまま認める」ことが、回復への最も論理的で責任ある選択であることをお伝えいたします。
「平気なフリ」は最大のコスト:当たり前の感情の偽装が引き起こす脳の過負荷
強がりが回復を妨げる最大の原因は、「感情の偽装」が脳に過度な負荷をかけるからです。
これは、前回までにお伝えした「思考の交通整理」の原則と全く同じです。
うつ病になるまでの間に、この感情の偽装を無意識に、もしくは「仕事だから」「私が責任持ってしなければ」と責任感によって行い続けていた結果、私たちの脳に極度の負荷がかかり続けていたのです。
Satsuki式:「弱さ」を論理的に認める3ステップ
強がりをやめることは、感情的な問題ではなく、「脳のエネルギー管理」という論理的な仕組みの問題として解決できます。
ステップ1:感情の「Yes/No」判定をデータとして客観視する
感情を「好き/嫌い」や「ポジティブ/ネガティブ」で捉えるのをやめ、「今、この瞬間にエネルギーが消耗しているか(Yes/No)」という論理的なデータとして客観視します。
「なんとなくこの人に会うと疲れるな。でも○○だから」と理由をつけて相手に合わせるようなことは感情の二重処理です。
「今、この人に会うこと」がエネルギーを消耗しているか?
⇒「Yes(疲労している)」
これを明確にするのが大事です。ここで「どうして疲れるのか?」を探る必要はありません。
ステップ2:自己犠牲をしないことが「責任」だと論理的に定義する
感情的に「わがままではないか?」と感じるかもしれませんが、これは「回復という最大の責任を果たす」ための行動です。
この認識に基づき、「未来の責任を果たすために、今は休息を選びます」という論理で自己申告します。
仕事でもそうですが、休職中・退職済みの方のプライベートにも同じことが言えます。
「今日はきつい。でも知人から誘われている外出がある。」という場合、自己犠牲で外出を選ぶとします。その結果、外出先で更に体調が悪くなったり、翌日以降にぐったりと動けなくなったりして、結果的に知人や奥さんにもっと大きな迷惑や心配をかけてしまうということも考えられます。
長い期間で見ると、私の場合は長年に渡って自己犠牲を無意識や責任感でやり続けた結果、3年経っても完治しない病気に自分を追い込みました。
ステップ3:最小限の自己肯定=「事実」で承認する仕組みを作る
自己肯定感を「感情」ではなく「事実」で積み上げる仕組みを作ります。
私たちはうつ病と闘っています。それで体調が安定しないのは「当たり前」です。体調が安定しないからと自己嫌悪に陥ったり、体調が安定しているように振る舞う必要はありません。
その体調が安定していない中で、「ドアを開けて外の空気を吸った」「太陽に10秒当たった」のは良いことです。
状況を客観視して、その中の自分を認めることが重要です。
強がり卒業後の人間関係:「弱い自分」を論理的なシールドにする方法
強がりをやめると、人間関係に不安を感じるかもしれません。しかし、あなたの「弱さ」(体調の不安定さ)は、逆に人間関係における論理的なシールドになります。
私はこれをせずに仕事を長年続けてきました。その結果、「あいつに頼んだら、なんでも成功させてくれる」という過度な期待を背負うことになりました。「ミスターパーフェクト」と呼ばれるようになりましたが、その裏には私の大きな自己犠牲がありました。
本当の状況は「無理をし続けているのだから、きつくて当たり前。」でした。
それなのに「まだできる。きつくない。」「自分はまだできる。」と感情の二重処理を無意識(習慣)と責任感で続けました。
実際、「きつい」「疲れた」という言葉を口にすることを嫌っていました。その言葉が出そうになると、ぐっと飲み込んだり、「きつぅ・・・くない!」と否定したりしていました。
まとめ:「強がりをやめる勇気」は、回復への最も論理的な近道である
「寒い日には震えているのは当たり前」という事実を、私は受け入れる必要がありました。
強がりをやめることは、わがままや弱さではありません。それは、あなたの回復という、未来への責任を果たすための最も論理的で賢明な選択です。
強がりという不採算事業を停止し、回復という最大の資産に投資を始めましょう。
合わせて読んでほしい:
人間関係の「交通整理」:エネルギー消耗を防ぐSatsuki式距離感と回復を優先する断り方
【Satsuki式習慣】「塵レベル」でOK!完璧主義を避けて挫折しない習慣の作り方(再発防止論理編)