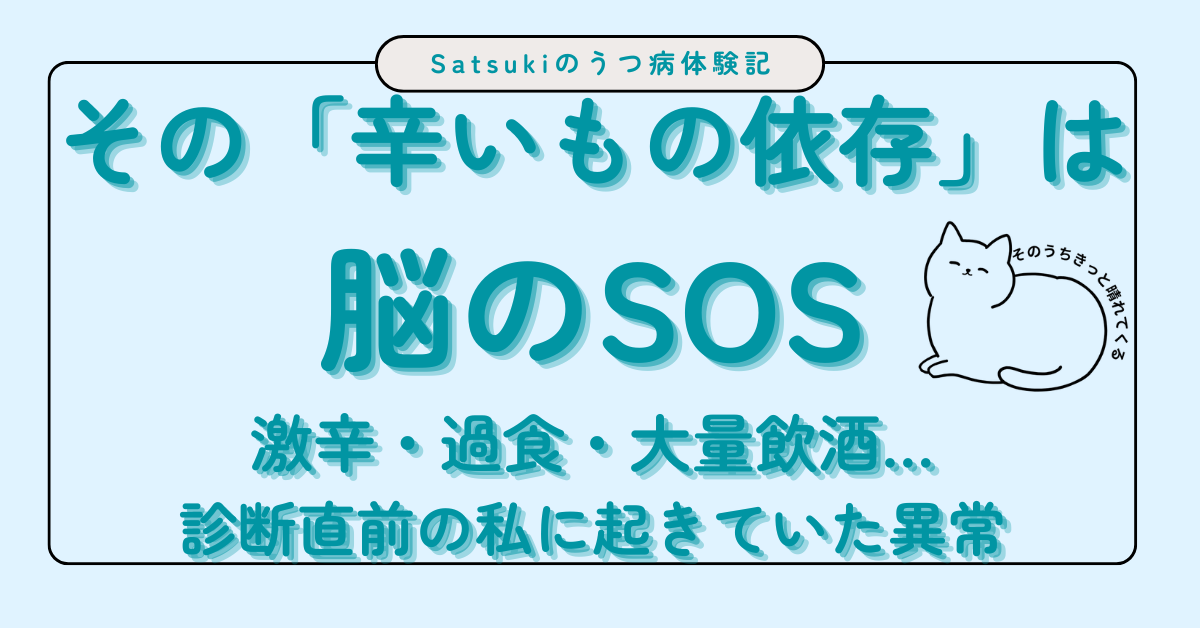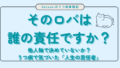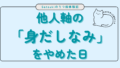はじめに:いつもとは違う行動
今回は、私が重度のうつ病と診断される直前の時期に見られた異常行動についてお話をしていきます。
診断されたからその日から「うつ病」というわけではなく、脳の機能は徐々に蝕まれています。それに自分で気づいているかどうかというところが重要なのですが、なかなか気づけるものではありません。
本人は、「いつもの自分として考え、いつもの自分として行動をしている」のです。そこに、「これはいつもの自分の行動ではないな」という気持ちが少しでもあれば異変に気付くことはあるかもしれません。
私は、行動の変化が「徐々に」だったこともあり、「疲れているんだろうな。」とか「気分転換が必要なのかもな。」程度にしか思っていませんでした。
その結果、うつ病と診断されるまで状況を悪化させ続けたのだと思います。今回は、その異常行動にフォーカスしてお話していきます。
皆様の「いつもの自分ではないかも?」の気づきの助けになれれば幸いです。
とにかく激辛なものが食べたい
その頃を振り返った時に自分で一番ぞっとするのが、すごく激辛なものを欲していたということです。
私は元々、辛いものよりも甘いものを好む傾向がありました。仕事の合間に食べるために、チョコレートや個包装の羊羹を常備していたほどです。
カレーでも麺類でも、ピリ辛くらいまでしか食べることはなく、一味唐辛子をドバドバかける、カレーはいつも10辛、のような辛いもの好きでは決してありません。カレーは頑張ったら2辛を食べられる、くらいの味覚です。
それが、最初は辛い味付けのお菓子を買うようになり、お酒のおつまみ用の辛い珍味に手が伸びるようになりました。そして、それに一味唐辛子を足すようになります。最終的には、料理用に売っている輪切りにしてある鷹の爪を、ポテトチップスのように袋から直接口に運んでいました。
激辛なものを欲するメカニズム
辛いものを無性に欲する心理の背景には、主に脳の働き(報酬系)とストレスが深く関わっています。
辛いもの(特に唐辛子のカプサイシンなど)は、味覚ではなく、舌の感覚神経が感知する「痛み」や「熱さ」といった刺激の一種です。この刺激に対して、脳はそれを打ち消すための強力な報酬を用意することで、私たちは辛いものに「やみつき」になります。
辛いものを欲する主な心理メカニズムとして、以下の4つが挙げられます。
脳内麻薬(β-エンドルフィン)による快感
ドーパミンによる「もっと欲しい」という欲求
ストレスからの「一時的な逃避・解消」
栄養不足や体温調節
心理的な要因だけでなく、身体的な要因として辛いものを欲することもあります。
【総括】この頃の私は、脳の報酬系が完全に暴走し、外部からの強い刺激でしかストレスを処理できなくなっていたのだと思います。
その頃の私は、無意識にストレスから離れる方法を模索していたのだと思います。そして、うつ病という「脳の通信制限」のせいで、五感もかなり鈍くなっています。実際、鷹の爪を丸かじりしていても、そこまで「辛い」という感覚はありませんでした。
鷹の爪の20g入りくらいの袋を1週間に1袋ペースで食べていましたので、さすがの妻も苦笑いしていました。それでも私は食べたくて、お願いして買ってきてもらっていました。
ちなみに、私は今、鷹の爪を料理の一部として食べることはありますが、それ単体で口にすることはありません。辛くて無理です。
休日の過食が驚くほど増える
仕事がある日は、休憩時間をとることがないほど働いていました。ですので、帰宅してからの晩御飯以外は、妻が作ってくれたおにぎりを作業の合間に口に頬張る程度の食事でした。あとは、エネルギー不足を感じた時に食べるチョコレートや一口羊羹程度しか口にしません。
しかし、休日は一日家にいます。家に会社のパソコンを持ち帰っていましたので、家で仕事をすることはありました。ただ、そこは職場とは違うので、間食は可能でした。
私は元々、間食をあまりしません。脳のエネルギー補給、気分転換という意味合いで少量を口にすることはありましたが、量を食べてお腹を満たすという感覚はほぼありませんでした。
それが、この頃は買い物の度にお菓子を買ってもらい、家で食べていました。気がつけば何かを口に運んでいる状態が常態化していました。ちなみに、重度のうつ病と診断される直前の休日には、1日で5㎏体重が増えるという異常事態が、普通に起きていました。
過食が起きる心理メカニズム
過食が起きる心理メカニズムは複雑で、単なる食欲の問題ではなく、感情(ストレス)と脳の報酬系が深く関わる行動として理解されています。特に、空腹ではないのに食べてしまう行動は「感情的な過食(エモーショナル・イーティング)」と呼ばれます。
過食を引き起こす主な心理メカニズムは以下の通りです。
ストレスとコルチゾールによる生理的変化
強いストレスを感じると、体はそれに対抗するために副腎からコルチゾールというホルモンを分泌します。
脳の「報酬系」の暴走(依存的サイクル)
高カロリーな食べ物や、特に糖質は、コカインなどの依存性薬物と同じように、脳の報酬系(快感を感じる神経回路)を強く刺激します。
感情の回避・処理の代替行為
過食の最も大きな心理的要因は、不快な感情やストレスを適切に処理できない場合に、一時的にその感情から逃れるための「対処行動」として食べ物を利用することです。
この頃の私は「過食」という自覚はまったくありません。仕事中は、「仕事に集中しなければならない」という、これまた「イカれた責任感」が勝るのでほぼ食べ物を口にしません。ですので、勤務日は痩せて、休日は太るというサイクルを自覚なしに行っていたのでしょう。
今の私の体重は55㎏です。この頃の私は、今よりも12㎏太っていました。アメリカ留学で食生活が変わって激太りした時でも62㎏になって驚いていたくらいです。どれだけ無自覚で、1日中食べ続けていたのかと考えると、自分でも恐ろしくなります。
アルコールの量が急激に増える
私は、体質的にはアルコールに強い体質です。幼い頃から身近な大人たちは浴びるほどお酒を飲んでいるような環境だったので、アルコールに抵抗感もありません。
ただ、学生時代から夜中に勉強や作業をする習慣がありました。ですので、年齢的にお酒を飲めるようになった後も、夜中の時間を有効活用したいという理由で日常的にはお酒を飲みませんでした。
仕事での飲み会や、何かお祝いなどの節目など特別な日には喜んでお酒を飲みます。それでもアルコールを飲んでしまうと「夜中に勉強ができない」「夜中に仕事ができない」「夜中に本が読めない」「車の運転ができない」など、デメリットが多いので晩酌という習慣はずっと持っていませんでした。
それが、気がつけば勤務日・休日関わらず、晩御飯の時にはお酒を飲むようになりました。妻はほとんど飲みませんので私だけです。そして気がつけばかなりの量を毎日飲んでいました。翠というジンのお酒を好んで飲んでいたのですが、アルコール度数は40度です。それの720ml瓶を一人で3日に1本のペースで飲み干していました。
それなのに飲んでいても「酔っている」という感覚はありませんでした。元々強いとはいえ、今の感覚とは違うものです。おそらく、ストレスのせいで飲酒前時点ですでに脳機能が低下していることで、アルコールによる脳機能の低下を感じにくい状態にあったのではないかと推察します。
頭の回転が悪くなることを不快に感じて、あまり日常的にはアルコールを飲まなかった私が、アルコールの影響による脳機能の低下を感じないということは、今となっては異常事態だったと分かります。
飲むアルコールの量が増える心理メカニズム
飲むアルコールの量が増える心理メカニズムは、脳の報酬系(快感のシステム)への作用と、ストレス対処のための行動の強化という2つの要因が複雑に絡み合って進行します。
このメカニズムは、最終的にアルコールへの依存を形成し、飲酒量を自分の意志でコントロールできなくなる状態につながります。
脳の報酬系の異常と飲酒量の増加
アルコールは、脳内でドーパミンという神経伝達物質の放出を増やし、快感や高揚感をもたらすことで「報酬系」を強力に活性化させます。この快感が、飲酒を繰り返す最大の動機となります。
ストレス対処としての飲酒の習慣化
アルコールを飲む動機が、気分を良くすること(高揚)から、ネガティブな感情を避けること(ストレス対処)へと変化していくことも、飲酒量が増える大きな要因です。
この頃飲んでいたお酒は、飲みたくて飲むという感覚よりは「飲まないと眠れない」という感覚だったように思います。ぐるぐると回り続ける無駄な思考を止めるために飲んでいたように思います。眠るために飲んでいますが、結果的に睡眠の質の低下につながる悪循環でした。
それでも、飲まないと思考が止まらず寝付けないので、究極の二択だったかもしれません。
深刻さに気付けない恐怖
今思い返してみると、明らかな異常行動です。だいぶ回復している今は、妻と一緒に「あの頃は本当に異常だったよね。」と笑い話になっています。しかし、その時点での自分は異常であることに気づけていませんでした。
そして、妻は異変には気づいていたようですが、「頑張っているからストレスも溜まっている。この行動はストレス解消の一環だろうから、それを止めると更にストレスを溜めてしまうかもしれない。」と敢えて止めなかったようです。
代わりに「会社を辞めた方がいい」とずっと言っていたので、妻の判断が一番冷静で的を得ていたのだと思います。
自分で気づかなければ、病院に行くことも異常行動を抑制することもできません。私は結局、病院に行ったのも会社からの苦し紛れの勧めがきっかけでした。そのまま退職していれば、適切な治療も受けることなく、無理に次の職場に移っていたかもしれません。
自分の状態を正確に把握することが、うつ病と戦っていくことの第一歩であり、最重要事項なのです。
いつもの自分」ではないサインをチェックする
今、この記事を読んでいるあなたは、「もしかして自分のことかも」と感じているかもしれません。しかし、当時の私のように、その行動が「脳の機能が悲鳴を上げているサイン」だと気づくのは非常に困難です。
そこで、あなたの状態を正確に把握するための、当時の私に当てはまった3つのセルフチェックリストをご提案します。
自覚なき異常行動のチェックリスト】
- 刺激への依存
強い刺激(激辛、大量の糖質、アルコール)がないと、心の安定やリラックスが得られない状態になっていないか? - 生活の極端な二極化
仕事のある日と休日で、飲酒量や食生活が極端に変わっていないか?(仕事で我慢している反動を休日に爆発させていないか?) - 機能的な摂取
食べる・飲む行為が「楽しむため」ではなく、「不安な思考を止めるため」や「強制的に眠るため」の手段になっていないか?
もしこれらの項目に当てはまる場合、それはあなたの心が「一時的な逃避行動」でしかストレスに対処できていないサインかもしれません。
最後に:自己判断を避け、専門家の力を借りる
当時の私は、妻が「会社を辞めた方がいい」と冷静にアドバイスしてくれましたが、自分で病院へ行くことはできませんでした。
これらの異常行動の根底には、あなた自身の意思や性格の問題ではなく、「ストレスによって脳機能が低下し、報酬系が暴走している」という脳のメカニズム上の問題があります。
この状態は、気合や精神論では解決しません。
自己判断で「ストレス解消だ」と見逃すのではなく、必ず心療内科、精神科、または職場の産業医など、第三者の専門家に相談してください。それが、事態を悪化させないための最も重要な一歩であり、自分自身の人生に対する責任でもあります。
これらの異常行動の根本原因である「脳の疲弊」と「自律神経の乱れ」を改善し、二度と外部刺激に頼らない安定した心を作るには、具体的な栄養と習慣が必要です。
【重要】免責事項と信頼性について
ここに掲載している内容は、すべて私個人の実体験と、一般的な知識に基づいてお話ししています。
この記事は、医師や医療専門家による医学的な診断、治療、またはアドバイスを代替するものではございません。
医学的根拠はございません。専門的な治療が必要な場合、必ず内科・脳神経外科、または心療内科・精神科などの専門医の意見を仰いでください。
当記事を参考に、読者の方が下した判断や行動の結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
合わせて読んでほしい:
【再発防止のための習慣】自律神経を整える習慣:マグネシウムと発酵食品が守る「第二の脳」(腸)の力
【再発防止のための習慣】食べて再発を防ぐ:脳の「通信速度」を上げる「天然の抗炎症剤」オイルの話
【再発防止のための習慣】心の安定に欠かせない「脳の材料」を無理なく摂る方法