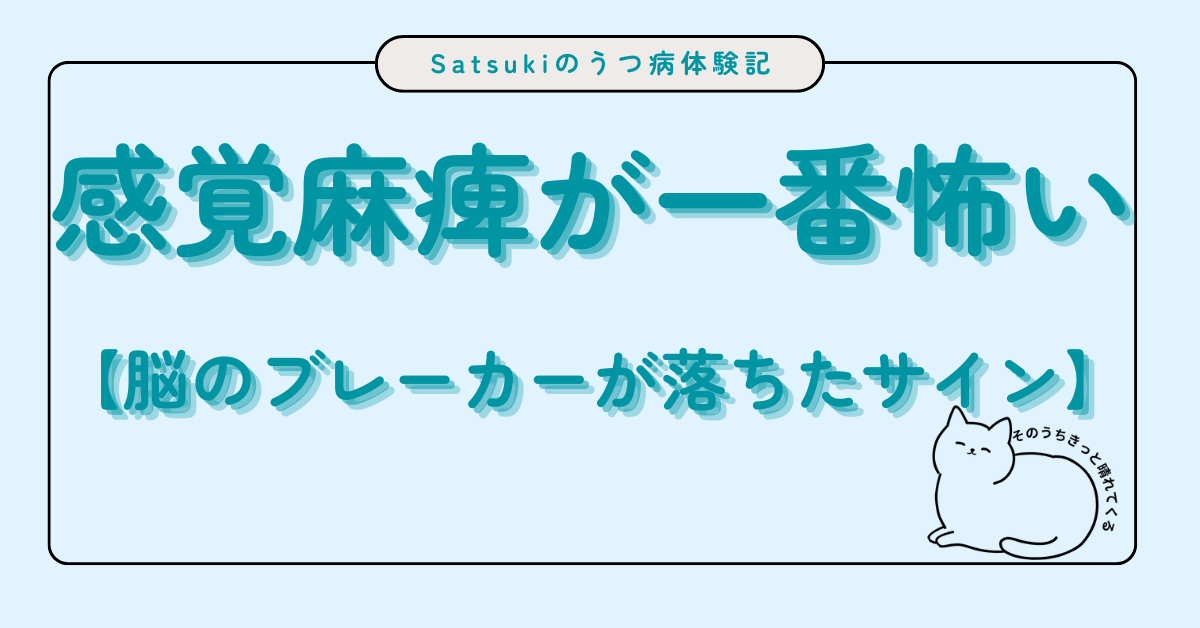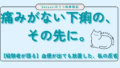はじめに:「嫌な気持ち」が消えた時の本当の怖さ
ストレスフルな状況に置かれているのに、「何も感じない」状態になったことはありませんか? 身体は鉛のように重く、頭も働かないのに、「もうやめたい」という切実な感情さえ湧いてこない。
当時の私は、「痛みがない下痢」と同様に、感情にも麻酔がかかったような状態でした。それは、頑張りすぎた脳が、これ以上壊れないために、自ら感情をシャットダウンしたサインです。この「感覚麻痺」こそ、うつ病の症状の中でも最も気づきにくく、一番怖いサインだと、私は経験から断言します。
この記事では、私が体験した感覚麻痺の具体的なサインと、そこから脱出して回復への一歩を踏み出す方法をお伝えします。
感覚麻痺のメカニズム:なぜ感情が「ゼロ」になるのか?
感覚麻痺(感情鈍麻)とは、嫌な感情(ネガティブ)だけでなく、嬉しい感情(ポジティブ)も同時に消えてしまい、喜怒哀楽の感情の振れ幅が極端に小さくなる状態です。
これは、脳の扁桃体などが、ストレスという大量の負荷に耐えきれず、まるでブレーカーを落とすように自己防衛のために機能をシャットダウンした状態だと理解されています。感情が消えることで、一時的に脳を休ませようとしているのです。
しかし、この状態が続くと、以下の3つの危険なサインを見逃しやすくなります。
経験者が語る:私が体験した「感覚麻痺の怖いサイン」
私が実際に経験した、「感覚が鈍っている」というSOSサインは以下の通りです。
疲労の警告が消えた:無理な長時間労働でも「もうやめたい」と感じない
身体は明らかに疲弊しているのに、「休むべき」という切実な感情や、仕事への「嫌だ」という感情が湧かなくなりました。振り返ってみて、確かにこんな感情を持っていたかもと自覚できますが、当時はその感情の存在にも気づいていませんでした。
まるでロボットのように、体力の限界を超えても「まだ頑張れる」「やるべきだからやる」と思い込んでしまう状態。これは、感情によるブレーキが完全に壊れていることを示していました。この無感情こそが、私を最も危険な状態へと引きずり込みました。
好きなものへの興味喪失:「好き」という感情が湧かない
かつては熱中していた趣味や、元気をもらっていた音楽、好きなアニメを見ても、「ふーん」で終わってしまう感じです。好きだった感情をどこかで忘れ去ったような、遠いところにあるものを見るような感覚でした。「どうでもいい」と感じるこの興味喪失(アパシー)は、脳の疲弊が最も強く表れるサインでした。
興味や楽しさといったポジティブな感情の消滅は、あなたの心のエネルギーが底を尽きかけていることを示しています。
自分の体調不良に危機感が持てなかった
前回の記事で語った「血便が出ても痛みがない」という経験も、この感覚麻痺と深く結びついていました。
痛みがないことや、毎朝の下痢が習慣化したことで、「自分の体は壊れている」という危機感を持てなくなっていたのです。心が「嫌だ」「怖い」と感じなくなった結果、身体の警告にも気づけなくなり、病状を放置することに繋がりました。
「感覚麻痺」と「血便の無痛」の共通点
私の体験から言えるのは、体と心は連動して感覚をシャットダウンするということです。
どちらも、「これ以上のストレスは受け入れられない」という、あなたの脳からの最終通告です。この状態にあるうちは、無理に頑張ろうとせず、まずは「休むこと」に意識を集中することが大切です。
感覚麻痺から脱出する「回復への一歩」
感覚麻痺は回復しない病気ではありません。休養と治療で脳の負荷が下がり、機能が回復すれば、必ず感情は戻ってきます。
まずは自分に「休む許可」を出す
休むことへの罪悪感や「イカれた責任感」こそ、感覚麻痺を生んだ原因です。「これは脳が命じる絶対安静だ」と割り切り、物理的に仕事や人間関係から距離を置きましょう。負荷を下げることが、感情のスイッチを再起動させる唯一の方法です。
小さな感情の「種」を拾い直す
「好き」という感情は、突然戻ってくるものではありません。回復期には、「味覚」など、原始的な感覚から拾い直す訓練をします。
「感じられた」という小さな体験を意識的に探すことが、感情を呼び戻す訓練になります。「感じられない自分」を絶対に責めないでください。
失った感情は必ず戻ってくる
私がうつ病の治療が本格化し、心が回復に向かい始めた時、普段食べていたものがその日突然、すごく美味しかった日のことを今でも覚えています。それは森永製菓のダースチョコレートでした。すりガラス越しにぼんやり見えていた世界が、一部分だけ鮮明に色付いていくような感覚。それは、「まだ自分には世界の色を感じる感情が残っていた」という安堵の瞬間でもありました。
今「無」の状態にいるあなたへ。
失った感情は、あなたが回復するのを待っています。必ず戻ってきます。自分を責めず、一歩ずつ回復への道を進みましょう。
【重要】免責事項と信頼性について
ここに掲載している内容は、すべて私個人の実体験と、一般的な知識に基づいてお話ししています。
この記事は、医師や医療専門家による医学的な診断、治療、またはアドバイスを代替するものではございません。
医学的根拠はございません。専門的な治療が必要な場合、必ず内科、または心療内科・精神科の専門医の意見を仰いでください。
当記事を参考に、読者の方が下した判断や行動の結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
【感覚が麻痺するほど頑張ってしまうのは、『イカれた責任感』に縛られているからです。自分を責めずに休むための具体的なマインドセットは、こちらの記事で詳しく語っています。】