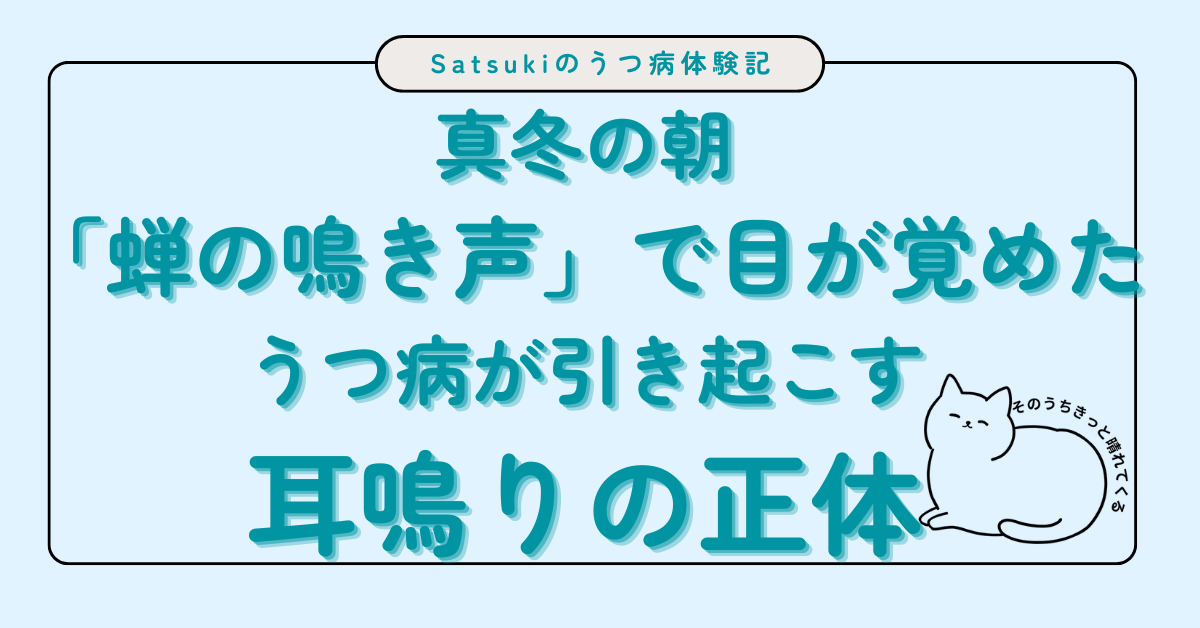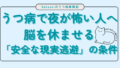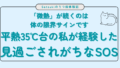今回は、うつ病との闘病中に常に付きまとっていた「耳鳴り」についてお話をしていきます。耳鳴りって、大したことないと正直侮っていたのですが、じわじわと精神力を削られていくような感覚で不快でした。
これは私の体験談です。その内容に、噓偽り、誇張はありません。しかし残念ながら、私は医学的専門知識を持ち合わせておりません。必要に応じて医師の指示を仰ぐようにお願い致します。
耳鳴りとは
皆様も経験したことがあるのではないでしょうか。私はうつ病になる前から、ちょこちょこ起きている現象だったので身近な存在なのですが、人によっては身近ではない人がいるのかもと想像しています。
原因の特定は難しいようですが、加齢や耳の疾患、血管や脳の病気。ストレス、疲労、睡眠不足で起きることが多いようです。最近は、ヘッドホンやイヤホンの大音量で耳の細胞がダメージを受けてしまい耳鳴りが発生することも増えているそうです。
耳鳴りのメカニズムはまだ完全には解明されていないようですが、最も有力な説は「内耳の有毛細胞の障害」と言われています。(※まだ解明はされていません。)
私が体験した耳鳴り
私が経験した耳鳴りは、4つの種類があります。
「キーン」という高い音の耳鳴り
これは常に鳴り続けているような感覚の耳鳴りでした。高い金属音のような「キーン」「ピー」という表現になるでしょうか。静かな時に聞こえることも多く、この音が嫌いでテレビをつけたままにしていることも多くありました。
メカニズムを調べてみましたが、ストレスやうつ病によって自律神経が乱れ、交感神経が優位になると、血管が収縮して内耳の血流が悪くなります。また、脳が過敏になり、通常なら気にならない音や、ごくわずかな信号を耳鳴りとして認識してしまう「聴覚過敏」が起こることが関係していると考えられているようです。
「ザー」「ゴー」という低音の耳鳴り
これらも頻繁にありました。ボイラーの近くに立っているような音だったり、風量最大のエアコンの前に立っているような音がする耳鳴りです。これが鳴る時は、飛行機に乗った時のように耳が詰まったような感覚が伴うことが多かったように思います。これは周りの音が聞こえにくいこともありましたので、かなり気になる迷惑な耳鳴りでした。
これも高い音の耳鳴りとメカニズムは変らないようですが、それに加えて肩や首のこりも関与しているのではないかという考察も見られました。
蝉が鳴くような耳鳴り
私はこれが一番嫌いでした。真夏の森の中に立っているような、「ワシワシワシワシワシ・・」。一番うつ病がひどい頃は、毎朝これで目が覚めていました。妻に「蝉がすごいね。ベランダにたくさん来てるのかな。」と質問して、怯えさせたことがありました。なにせ11月だったので。
これはうつ病になった際に、感覚の感度が高まることに原因があると言われています。これは、脳が音の刺激にも過剰に反応しやすくなってしまっている状態です。
通常なら無視できる、ごくわずかな音や信号(例えば、耳の細胞が発する微弱な電気信号のようなもの)を「音」として認識してしまうのです。この状態は、聴覚過敏ともよばれ、実際に聞こえている音ではない「幻聴」を引き起こしてしまうようです。
この体験は、うつ病が『心の問題』だけでなく、『脳が感覚を過剰に処理するという身体症状でもある』ことを私に強く教えてくれました。
耳元でシンバルをたたくような耳鳴り
これは抗うつ剤の離脱症状として起きるようです。病院に行くエネルギーすら確保できず、病院に行く日程をずらした時に起こりました。それまで飲んでいた薬も切れてしまい、服薬を中止した状態が4日できたのですが、その期間に起きました。
頭を動かした時や、眼球を動かした時に耳元でシンバルを盛大に「ジャンジャンジャンジャン・・・」と鳴らされるような音がしました。精神的にも弱っているので恐怖でしかなかったのですが、医師に相談した結果それが離脱症状だと分かりました。
急に服薬を中止したりすると起きることがあるようです。原因は、薬によって調整していたセロトニンの量が急激に変化するので、その変化に脳がついていけなくなってしまうのだそうです。
耳鳴りも結構大変
たかが耳鳴りではありますが、いつも聞かない音が聞こえたり、まわりの音が聞こえないレベルの音が鳴るのはやはり不安です。そして、想像以上にストレスになります。私は睡眠導入剤を飲んでいましたので、私は耳鳴りのせいで一晩中眠れない、ということはなかったですが寝付く妨げになる方もいらっしゃると思います。
結果としてストレスと睡眠不足を引き起こしてしまい、うつ病が悪化してしまうということもあるのかもしれません。現に私は真冬にも関わらず、蝉の声で起こされていましたし。
今回は、耳鳴りが起きるという症状を知っているだけで不安材料が減る方もいらっしゃるかもしれないなと思い、書かせていただきました。
耳鳴りの不快感を減らすためのセルフケア
耳鳴りが続くと、その不快感と不安からストレスが増幅し、症状が悪化するという悪循環に陥りやすくなります。日常的に起きる不快感を軽減するために、私が実践したり、医師から提案されたりした「脳と耳を休ませるためのセルフケア」を3つご紹介します。
音響療法(小さな音で「脳の関心」を逸らす)
耳鳴りは、脳が過敏になり、微弱な信号を「音」として過剰に認識してしまうことで起こります。最も避けたいのは、静かすぎる環境です。静寂は、脳の関心を耳鳴りの音に集中させ、さらに耳鳴りを大きく感じさせてしまいます。
リラクゼーション(自律神経の乱れを整える)
高い音や低い音の耳鳴りには、ストレスによる自律神経の乱れや、首・肩のこりが関与している可能性が高いです。血管の収縮で内耳の血流が悪くなっている状態を改善するために、意識的に体を緩めましょう。
栄養補給(内耳と神経伝達物質をサポート)
耳鳴りのメカニズムには、脳の神経伝達物質のバランスや内耳の細胞の障害が関係していると考えられています。私自身、うつ病の治療においては、食事やサプリメントから「脳の材料」を補給することを徹底しました。
特に、血管の収縮を防ぎ、神経の興奮を鎮める働きがあるマグネシウムは、耳鳴り対策としても注目されています。
酷い時は耳鼻咽喉科へ
耳鳴りは、脳の神経伝達物質のバランスが崩れたり、自律神経が乱れたり、脳の過敏な反応が起きたりすることで発生するのだろうという仮説は立っています。ただ、まだまだ研究中のようで直接的な因果関係は解明されていないようです。
それゆえ、医師によってはうつ病と耳鳴りは関係がないとおっしゃる方もいらっしゃいました。そして当事者から医師に対して、耳鳴りの状況を伝えるのがとにかく難しい。心療内科なのか耳鼻科なのか、脳神経外科なのかもよく分かりません。
私もだれに相談したらいいか分からず、いろんな医師に相談しました。それでもメカニズムがはっきりしていないので、お医者さんでも「原因は○○ですね。」と言い切るのはなかなか難しいようです。
今回はあちこちで集めた情報をまとめさせていただきましたが、あくまで私の体験談です。医学的根拠はありません。
耳鳴りが続く場合は、なにかしら他の病気が隠れている可能性もありますので、ぜひ医師にご相談ください。最初に行くのは耳鼻咽喉科がいいのではないかとおっしゃる方が多かったように思います。
【重要】免責事項と信頼性について
ここに掲載している内容は、すべて私個人の実体験と、一般的な知識に基づいてお話ししています。
この記事は、医師や医療専門家による医学的な診断、治療、またはアドバイスを代替するものではございません。
医学的根拠はございません。専門的な治療が必要な場合、必ず内科・脳神経外科、または心療内科・精神科などの専門医の意見を仰いでください。
当記事を参考に、読者の方が下した判断や行動の結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
合わせて読んでほしい:
【再発防止のための習慣】心の安定に欠かせない「脳の材料」を無理なく摂る方法
【再発防止のための習慣】自律神経を整える習慣:マグネシウムと発酵食品が守る「第二の脳」(腸)の力