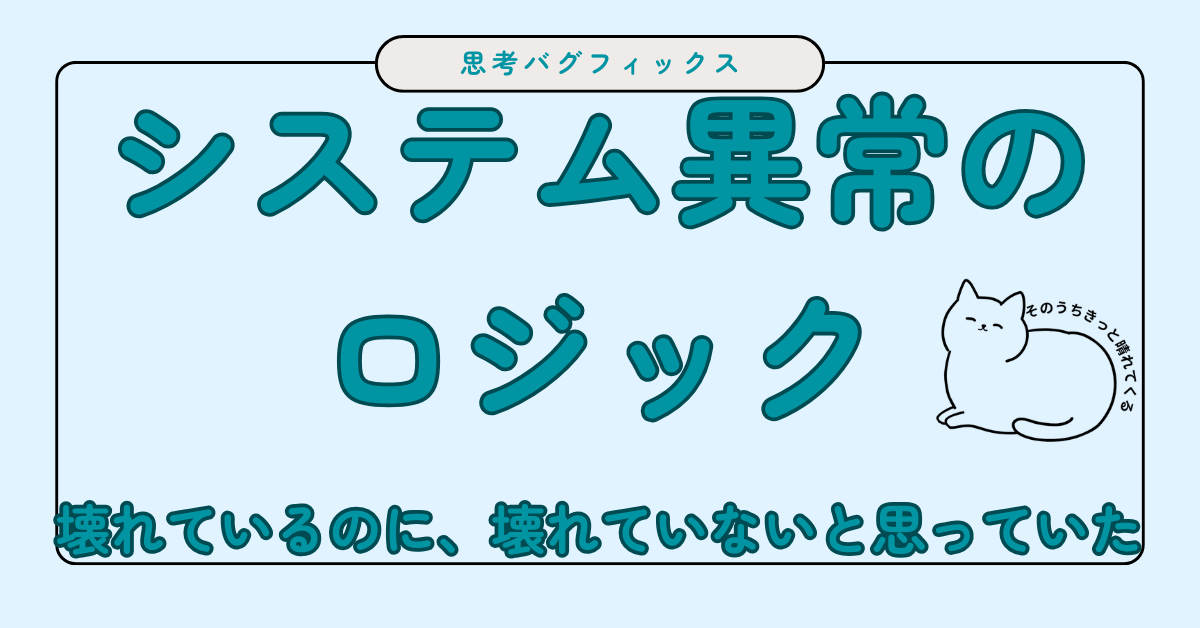はじめに:すべては、静かに始まっていた
私の生存システムに重大な不具合が認められてから、もう3年になる。
このブログでは、
私のシステムが限界を迎え、強制停止し、休職、そして現在の安定に至るまでの道筋を、論理的に可視化された記録 としてまとめている。
いま限界ギリギリで稼働している人。
家族の変調を感じている人。
「もしかしたら自分も…?」と不安を抱えている人へ。
この記録が、あなたの“少し先の地図”になることを願っている。
フェーズ0:最初の異常値
― 仕事から離れても鳴り止まなかったSOSログ
あの日、私は仕事を休み、母の病院送迎のために車を走らせていた。
月に一度だけ、自分で希望を出して休める貴重な休日。
勤務先とは違う県に住む母のもとまで、片道3時間。レンタカー代も高速代もかかるが、それが当然だと思っていた。
理由は簡単で、そして複雑でもある。
母を守るのは私の義務だと信じていたから。
そしてその義務を果たすことが、私にとっての「コスト免除券」だったから。
必死に働き、疲労困憊の日々の中で、
“親の要求に応える=存在を許される”
そんな構造が、幼い頃から当たり前になっていた。
だから私は、往復6時間の日帰り運転を「当然」と処理していた。
けれど、その裏側で――
私のシステムは、すでに静かに崩壊し始めていた。
見逃され続けたログ
― リソース枯渇の「初期データ」
当時の私は、まだ自分の限界に気づいていなかった。
「仕事が嫌だな」
その程度の認識しかなかった。
社会に出てからずっと営業職で、ノルマと緊張の連続だった。
“苦しいのが普通”という古いOSが自分の中にあったから、
異常値を異常だと判断できなかったのだ。
しかし、私の体は1年以上前から確実にサインを送っていた。
頭痛:警告アラームの「常時発火」
中学生の頃から頭痛は日常だった。
だから私はそれを異常値だとは思わなかった。
大人になってからも、
目の奥がえぐれるような痛み、
嘔吐でしか緩和されない激痛が時々訪れていた。
けれどそれも、「いつものこと」と処理していた。
しかし――
限界の少し前から、私は知らないうちに
毎日ロキソニンを3回飲む生活 へ移行していた。
本人の認識と、実際の稼働状況が完全にズレていたのだ。
下痢:処理落ちした排出システム
腹痛はほとんどないのに、便だけが常時“液体モード”になっていく。
血が混ざる日が増えても、私は「またか」としか思わなかった。
気づけば2年以上、
“形のある便”を見ていなかった。
あれほど明確な異常値でさえ、私のOSは無視していた。
微熱:平熱35.2℃の体が「緊急稼働モード」に入るまで
これは唯一、体感としての負荷が強かった。
出勤時だけ体温が2度近く跳ね上がり、
頭がボアボアして視界がにじむ。
しかし、帰宅後には体温が急降下する。
だから私は「気のせいだ」と処理してしまった。
本当は体が、
“出勤を拒否していた” のだと
後になってようやく理解できた。
全システムが崩れた瞬間
― 理由なき涙が出た日
母を家へ送り届け、任務も終わった。
青空、好きな音楽、快適な速度。
帰れば、最愛の妻が温かいご飯を用意して待っている。
完璧なはずの帰り道だった。
なのに——
視界が突然、涙でぼやけた。
理由が分からない。
悲しくもない。
つらい記憶に触れたわけでもない。
ただ運転していただけなのに、嗚咽が勝手に漏れた。
近くのサービスエリアに滑り込み、
薄暗い車内で私はひとり、声を押し殺して泣き続けた。
あれはきっと、
システムが自分自身を守るために放った“最終アラート”
だったのだと思う。
その瞬間が、私が限界に気づいた瞬間だった。
風の日の始まり
― 強制停止、そして再構築へ
家に帰り、妻に告げた。
「仕事を辞めることにする。」
妻は迷わず言った。
「うん。そうしよう。」
そこから2ヶ月間、私は会社に知られないように
引き継ぎ・仕組み化・調整をひっそり進めた。
今振り返れば、
こんな状態でも会社が回るよう根回しし続けたのは、
完全に “バグ化した責任感OS” の所業だ。
正しい行動ではなかった。
でも当時の私は、それ以外の選択肢を持っていなかった。
結び
― 「異常値に気づく」という、当たり前の難しさ
限界を迎えて初めて分かった。
自分の異常値に気づくことは、驚くほど難しい。
私は長い間、
寒くても「寒くない」と言い、
怖くても「怖くない」と言い、
空を見上げる余裕すら忘れて生きていた。
あなたには、そうなってほしくない。
もし何かが“いつもと違う”なら、
それはすでに あなたのシステムが送っているサイン かもしれない。
限界サインの読み取り方や、
そこから再構築する方法については、
このブログにまとめている。
必要なときに、いつでも見に来てほしい。