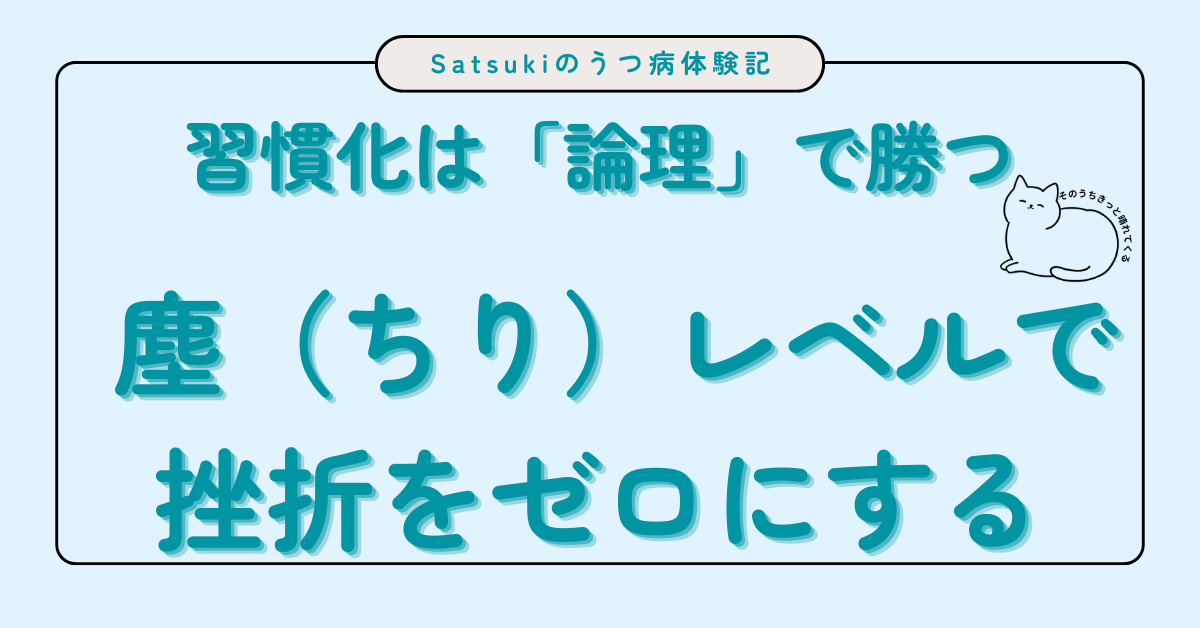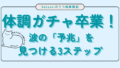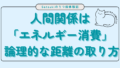はじめに:習慣化の罠「完璧主義」から逃れる
なぜ、うつ病から回復しようとする多くの人が「習慣化」に失敗してしまうのでしょうか?
それは、私たちの中に根強く残る「完璧主義」が、せっかくのエネルギーを消費してしまうからです。
調子が少しでも上向くと、「体調が良い今のうちに、あれもこれも習慣にしなければ」と考えます。例えば、「毎日30分ウォーキング」「毎日日記を丁寧に書く」といった、完璧な目標を設定してしまいます。
しかし、以前の記事でお伝えした通り、うつ病で疲弊した脳のエネルギーは非常に不安定です。頑張って活動しすぎると、必ず大きな反動が来ます。
習慣化の本当の目的は、「大きな成果を出すこと」ではありません。「安定した回復ペースを維持すること」にあります。
この記事では、完璧主義を回避し、「少しずつ」を確実に積み上げる、挫折しないための具体的な習慣化のルールを解説します。
Satsuki式:習慣を始める前の「エネルギー確認」
習慣を始める前に、それがあなたの不安定なエネルギーを浪費しない設定になっているかを、論理的に確認します。
ステップ1:習慣の「最小メリット」を定義する
その習慣を続けることで、あなたが得られる最小限のメリットは何ですか?これを明確に定義します。大きな成果ではなく、脳の回復につながる論理的なメリットに焦点を当てましょう。
| 習慣の例 | ❌ 危険な大きなメリット | ✅ Satsuki式の最小メリット(論理的な目的) |
| 散歩 | 「体力をつけて、仕事を再開できるようにする。」 | 「太陽の光を浴び、脳の充電効率をわずかでも上げること。」 |
| 読書 | 「うつ病に関する知識を増やし、完全に克服する。」 | 「思考の燃費を悪化させるネガティブ思考から、5分間、注意をそらすこと。」 |
大きなメリットを掲げてしまうと、その分やるべき行動が大きくなってしまいます。
ボールを投げる時に、「目の前にあるごみ箱に入るように投げる」のと、「20メートル先にいる友達に向かってボールを投げる」のでは必要な力も、体の動かし方も違います。
得たいメリット(目的)が大きくなれば、負荷は確実に大きくなるのです。最小で得たいメリットが何かを明確に決めましょう。
ステップ2:習慣が「トリガー」にならないかを確認
以前の記事で「体調悪化トリガー(予兆)」を発見しましたね。その習慣が、過去のあなたのトリガーと結びついていないかを論理的に確認します。
トリガーを避ける時間帯、場所、強度で設定されていることを確認してから、習慣をスタートしましょう。
始めようとする習慣が「体調悪化トリガー」になってしまうのであれば、本末転倒です。上の例のように直接結びついていれば分かりやすいと思います。
しかし、あなたの「体調悪化トリガー」が「7時間以下の睡眠」なのにも関わらず、「毎朝決まった時間に起きる」ことを習慣化しようとすると、始めようとする習慣が「体調悪化トリガー」になってしまうことは十分にあります。
実践:挫折しないための3つのルール
習慣化を成功させるカギは、「意志の力」ではなく「仕組み」です。挫折の要因となる「完璧主義」と「自己嫌悪」を避けるための3つのルールを適用しましょう。
ルール1:最低ラインは「塵(ちり)」レベルで設定する
習慣化の最も重要な目標は「やらない日をゼロにすること」です。そのため、習慣の最小行動量を「達成感が得られないくらい低いレベル」に設定します。
これは、行動科学で提唱されている「ベイビーステップ」の核心でもあります。
目標を下げることで、行動のハードルを極限まで下げ、「行動のスタート時」に脳が感じる抵抗をゼロにすることができます。
| 習慣 | ❌ 完璧な目標 | ✅ 最低ライン(塵レベル) |
| 散歩 | 30分、近所を歩く。 | 玄関のドアを開けて、外の空気を吸うだけ。 |
| 読書 | 1章読み終える。 | 本を開いて、タイトルを声に出して読むだけ。 |
| 日記 | 三行日記を丁寧に書く。 | ノートに日付を書いて、ペンを置くだけ。 |
「やらない日をゼロにする」ことに成功すれば、あなたは毎日エネルギーを温存しながら、回復への土台を確実に固めています。
最低ラインを理想に近いレベルで設定すべきではありません。「こんなことを習慣にできればいいな」のレベルではなく、「そんなことを習慣にしたところで何が変わるの?」くらいのレベルで設定しましょう。
まさに「塵も積もれば山となる」です。「塵レベル」を忘れないでください。
ルール2:「少し物足りない」くらいで止めるマインドセット
以前の記事で学んだ「投資マインド」を、習慣の実行中に適用します。
活動を終えた後に「8割できたからOK」とあえて残すことで、「完璧を求めなかった自分」に安心感を与え、脳の疲弊を防ぐことができます。
調子が良いとやりすぎてしまいます。私も毎日「エアロバイクを毎日30分漕ぐ」と目標を立てて、失敗したことがあります。
調子が良いと「もう少しできる。」とテンションが上がって、やりすぎます。調子が良い日に1時間漕いで目標を大きく超えたことで、その時は大きな達成感と満足感を得ました。しかし次の日から1週間程度、ベッドから出られないほど体調が悪化したのは苦い経験です。
「あともう少し」を積み重ねて、自分の成長につなげていく高校時代の部活のような状況とは、状況が異なることを肝に銘じておきましょう。
ルール3:記録は「感情」でなく「Yes/No」で
習慣の記録は、感情的な評価や反省を含めてはいけません。これは自己嫌悪のトリガーになります。
記録するのは、論理的な事実のみです。
❌ 間違った記録: 「今日は体調が悪くて、結局15分しか歩けなかった。自分はダメだ。」
✅ 論理的な記録: 「散歩:Yes(10秒でも外に出た)、読書:No」
「やった(Yes)か、やらなかった(No)か」の2択のみにすることで、失敗した日も自分を責めることなく、次の日に仕切り直すことができます。
再度確認してください。習慣化の最も重要な目標は、「やらない日をゼロにすること」です。
習慣の応用:失敗は「後退」ではなく「データ」
それでも記録に「No」が連続してしまうことはあると思います。新しいことに取り組むのですから、それは当然です。
そして習慣化の途中で「No」の日が続くことは、決して「後退」ではありません。それは、「習慣の設定に無理があった」という新しいデータです。
習慣化は、意志の力ではなく、論理と仕組みで達成できます。この仕組みを少しずつ改善していくことが、回復を自動化する最強のツールとなります。
まとめ:「習慣」は回復を自動化する最強のツール
習慣は、あなたの「体調ガチャ」を卒業させ、回復を自動的に進めるための仕組みです。
完璧を求めず、論理的な仕組みと最小限の行動で、着実に回復の土台を固めていきましょう。
この「習慣の作り方」を身につけたら、次はその習慣を崩壊させる大きな原因である「人間関係のストレス」にどう対処するか、具体的な方法を解説します。
合わせて読んでほしい:
「体調ガチャ」を卒業する方法:Satsuki式「思考の交通整理」で波を予測し、再発を防ぐ行動計画
【Satsuki式マインドセット】うつ病の「思考の燃費」を改善!紙とペンで客観視する「交通整理」の具体的方法